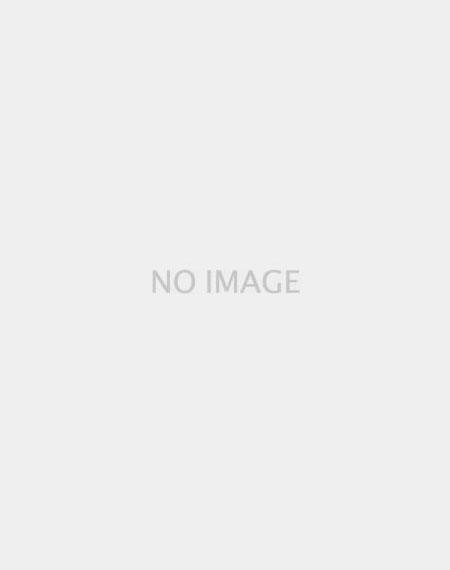ISO30414改訂の要点と今後の人的資本関連情報開示のポイント
-
コーポレート
ガバナンス Corporate
Governance - 指名・人財 Nomination/HR
- 報酬 Compensation
- サステナビリティ Sustainability
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
コンサルタント
石丸 萌
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
コンサルタント
前田 祐梨子
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
マネージャー
大石 英翔
■ サマリー
本メルマガでは、2025年8月に改訂版が公表されたISO30414に着目し、筆者らが重要と考える改訂ポイントを解説するとともに、今後日本企業に求められる人的資本関連情報開示の在り方について考察する
ISO30414は、企業が人的資本関連の情報開示に際して任意に活用することができる規格であり、定性・定量的な指標を体系的に提示している点、構造化した開示フォーマットを提示している点、そして組織の規模や業種に関わらず、あらゆる組織に適用できる点が特徴といえる。したがってISO30414 に準拠した開示を行う企業は、国内外の投資家から比較可能性の観点で好意的に評価されると考えられる
2025年の主な改訂内容としては、①各指標が新たに「要求事項」と「推奨事項」に分類されたこと、②コスト領域の定義において人的資本投資と経営戦略との関連性を重視する内容が記載されたこと、③人的資本ROIがより広範な人的資本投資を評価する算定式となったこと、④定着率に代わる指標として初年度離職率及び平均勤続年数が新たに導入されたこと、そして⑤コンプライアンス・倫理領域において人権に係る指標が新たに導入されたこと、の5点が挙げられる
企業は比較可能性の高い指標と自社独自の戦略・取組みの両面をバランスよく開示することが重要である。比較可能性が重視される指標はISO30414の国際基準が参考になると考えられ、独自性が重視される指標についてはその意義や定義、自社の戦略との関連性を説明することが求められる
企業は自社の経営戦略と人材戦略が一体となった価値創造ストーリーを構築し、それを土台とした将来像と現状のギャップを埋めるための人的資本経営の開示を通じて、単なる情報提供を超えて投資家や社会からの信頼を高めることが求められる
目次
1.はじめに
1-1 高まる人的資本関連情報開示への要請
2020年9月に経済産業省が「人材版伊藤レポート」を公表してから約5年の間に、日本企業における人的資本経営は大きく進展してきました。2023年には有価証券報告書における人的資本関連の情報開示が義務化され、さらに2026年3月期の有価証券報告書からは、「従業員の状況」欄において企業戦略と関連付けた人材戦略やそれを踏まえた従業員給与等の決定方針等についての開示を求める方針が金融庁から示されているなど¹、今後も人的資本に関する取組みと開示の重要性はますます大きくなることが見込まれます。
本稿では、2025年8月に改訂版が公表されたISO30414に着目し、筆者らが重要と考える改訂ポイントを解説するとともに、今後日本企業に求められる人的資本関連情報開示の在り方について考察します。
1-2 ISO30414の概要
ISO30414は、国際標準化機構(以下、「ISO」という。)が策定、公表している人的資本関連の情報開示に関する国際規格です。2018年に初版である「ISO30414: 2018」(以下、「2018年版」という。)²が、2025年8月に改訂版である「ISO30414: 2025」(以下、「2025年版」という。)³が公表されました。人的資本に関する幅広いトピックをカバーしており、領域ごとに詳細な開示事項が定義されています。2025年版では、11の領域区分(図表1)にもとづき開示事項が設定されています。
図表1
2025年版が取り扱う人的資本関連開示の領域

2025年版は、企業が人的資本関連の情報開示に際して任意に活用することができる規格であり、ISO30414に準拠した情報開示が企業に義務付けられているわけではありません。
同規格の特徴は、定性・定量的な指標を体系的に提示している点、構造化した開示フォーマットを提示している点、そして組織の規模や業種に関わらず、あらゆる組織に適用できる点にあります。また、グローバル・レポーティング・イニシアチブ(GRI)や統合報告イニシアチブ(IIRC)、サステナビリティ会計基準審議会(SASB)が策定する基準および枠組み、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)、国際財務報告基準(IFRS)S1、米国証券取引委員会(SEC)の開示規則、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)などの主要な国際基準等を参考に策定されています⁴。したがって、ISO30414に準拠した開示を行う企業は、国内外の投資家から比較可能性の観点で好意的に評価されると考えられます。
2.ISO30414改訂の要点
本章では、2025年版の改訂箇所のうち、人的資本開示に向けた検討に際して影響が大きいと思われる主な改訂内容について解説します。
2-1 要求事項の位置づけ
2025年版の主な変更点の一つは、各指標が「要求事項」と「推奨事項」に分類されたことです。2018年版では指標に対して要求事項と推奨事項の区別がなく、一律に提示されていました。ISO規格では要求事項とは、「客観的に検証可能な達成基準を示すものであり、規格への適合性を主張する場合に必ず満たさなければならない条件(仮訳)」⁵と定義されています。つまり、ISO30414は任意適用の規格でありながら、企業がISO30414に準拠した人的資本開示を行う場合には、要求事項として定められた指標については規格に沿った内容で開示する必要があります。ISOの要求事項は客観的な評価が可能になっていることから、ISO規格への準拠には第三者認証は必須とされておらず、自己評価により準拠を示すことが可能です⁶。2025年版では全69指標のうち7領域にわたる14指標が要求事項として定められています。この改訂は、投資家が企業の人的資本開示をより正確に理解し評価するにあたり、比較可能な指標に対する需要の表れと捉えられます。
2-2 コストの定義からみる人的資本投資の捉え方
コスト領域の定義についても変化がみられます(図表2)。2018年版では、「投資家」が人的資本への投資に対する「収益性」「非財務のリターン」を見るためのものとされていました。一方で2025年版では「ステークホルダー」が人的資本への投資がもたらす「経営の持続可能性」「経営戦略における人的資本の重要性」を理解するために重要であるとの位置づけとなっています。前述した投資家を意識した比較可能性の強化に加え、2025年版ではより広範なステークホルダーを意識した視点が取り入れられていることがわかります。ISO30414では投資家以外のステークホルダーとして、具体的に従業員・労働者、経営層・取締役会、地域やサプライチェーンのコミュニティ、顧客、政府や規制当局、格付け機関等を挙げており、組織がどのように人材に投資し、その成果や持続可能性を高めているかを示すことは、こうした多様なステークホルダーにとって価値があると説明しています。これは、企業が多様なステークホルダーを意識した経営を行うことが、結果的に中長期的な企業価値の向上や投資家リターンの最大化にもつながるという理解が進んだことの表れともいえるのではないでしょうか。その他、2018年版では人的資本投資に対する成果の測定・評価を重視した表現から、2025年版では人的資本と経営戦略の関連性を重視した表現へと遷移したことが読み取れます。「経営の持続可能性」という時間軸を含む言葉からは、より中長期の目線で人的資本投資がもたらす効果を評価する姿勢がうかがえます。
図表2
ISO30414におけるコスト領域の定義(抜粋)

2-3 人的資本ROIの算出方法
生産性の指標である人的資本ROIについては、その算出方法が改訂されました(図表3)。人的資本ROIとは、人的資本への投資から得られる価値を定量化する指標であり、人的資本投資の効率性と有効性を理解するうえで重要な指標とされています。人的資本ROIを測る際の分母となる人的資本投資の内容として、2018年版では給与と福利厚生のみだったのに対して、2025年版ではそれらに加えて外部労働力、採用、学習・開発、その他直接人的資本関連の投資も含まれるようになっています。外部人材や自社従業員の採用や育成にかかる投資も、将来的な収益に貢献する投資として捉えた定義であることがわかります。企業には、これまでのような画一的な人材管理ではなく、競争力向上につながる組織・人材を見極めた上でリスクとリターンの両面から最適な人的資本投資を検討していくことが求められます。
図表3
ISO30414における人的資本ROIの定義

2-4 定着状況の測り方
リーダーシップ・文化・エンゲージメントの領域においては、2018年版で設けられていた定着率の指標が削除されました。2025年版では新たに平均勤続年数と初年度離職率の指標が設けられ、これらが定着率に代わる指標と考えられます(図表4)。2018年版の定着率は、勤続一年以上の従業員数を一年前の従業員数で除して算出することが多いとされ、従業員を維持する能力を測る安定性指数とされていました。一方で、2025年版の初年度離職率は初年度中に離職した労働者数を同期間に採用された労働者総数で除して算出し、ISO30414ではこの指標は採用プロセスやエンゲージメントの潜在的な課題を特定するために重要であることが指摘されています。初年度離職率は、定着率と比較して1年間という短期的な傾向を測る指標であることは変わりませんが、定着した側ではなく離職した側を測るといったよりリスクフォーカスな考えが反映されています。また、平均勤続年数は組織全体の長期的な雇用の安定性を示すと考えられ、これを初年度離職率と組み合わせることで、短期的な離職傾向と長期的な雇用の安定性の両面から人的資本の定着状況をより多角的に評価することが可能になったといえます。
図表4
ISO30414における定着/離職状況を測る指標の定義

2-5 人権に係る指標の追加
コンプライアンス・倫理の領域では、新たに人権問題の件数、種類および結果の指標が要求事項として追加されました。人権問題は企業の評判や法的リスクに直結する可能性があることから、これを定量的に把握・報告することは人的資本をリスクマネジメントの観点からも捉えるという考えの広がりを示しています。この点は、ビジネスにおいて人権を考慮するべきという国際的な動向が反映された改訂といえます。
3.今後の人的資本関連情報開示のポイント
3-1 ISO30414の活用のポイント
人的資本に関する情報開示の主な読み手としては、投資家および自社の従業員、採用候補者などが挙げられます。本章では特に、投資家に対し人的資本を通じた価値創造ストーリーを訴求する観点から、ISO30414の活用方法をご提案します。
2022年に内閣官房の非財務情報可視化研究会が公表した人的資本可視化指針⁷は、人的資本に関する具体的な開示内容の検討にあたり、「比較可能性の観点から開示が期待される事項」と「独自性のある取組・指標・目標」の二つの類型を活用することを提示しています。開示に際しては、これら二つの類型に該当する開示項目の適切な組み合わせおよびバランスを確保する必要があるとされています。
「比較可能性の観点から開示が期待される事項」は、投資家が幅広い企業を対象に比較やスクリーニングを行う際に活用されることが想定されます。そのため、指標の定義や算定方法の決定にあたっては国内外の開示基準を参照するなど、他社との比較可能性に配慮することが肝要です。ISO30414は、国際的に広く利用されている基準であり、その定義に従って指標を開示することで、グローバルレベルで他社との比較可能性を確保することができると考えます。ISO30414の開示事項のなかで、具体的にどの事項が「比較可能性の観点から開示が期待される事項」に該当するかの明確な区分けがあるわけではありません。しかし、従業員全体および経営陣における性別・年齢などの属性の多様性を示す指標(日本においては特に女性管理職比率)や、人権問題の件数をはじめとするコンプライアンス関連の指標などは、一般的に、一定程度の水準の達成が最低条件として求められることから、横並びでの比較への投資家のニーズが高いと考えられます。また、企業の健全性を示す離職率のデータも、業種や企業規模に関わらず重要性の高い指標であると考えられます。
一方、人的資本を通じて企業価値を向上させていくための自社の戦略を投資家に伝えるには、自社固有の戦略や取組みについて説明することが不可欠です。そこで、「独自性のある取組・指標・目標」の開示が必要になります。こうした開示に際しては、人的資本に関する各開示事項が自社の価値創造ストーリーの中でどのように位置づけられているか、また自社の企業価値向上にどのようなプロセスで寄与するかを、具体的に示すことが求められます。
人的資本可視化指針は、「独自性のある取組・指標・目標」をさらに2つに分類し、①取組みや開示事項そのものが企業に固有である場合と、②開示事項自体は他社と共通でありつつ、その開示事項を選択した理由に企業固有の戦略やビジネスモデルが影響する場合のそれぞれについて、開示のポイントを提示しています。前者の場合は、他社との比較が目的ではないため、関連する指標の自社としての定義を説明し、時系列での進捗を意識した開示を行うことが肝要です。一方後者の場合は、自社固有の戦略やビジネスモデルと関連付けた説明を行ったうえで、他社との比較可能性を確保することが求められるケースもあります。そのため、国際規格であるISO30414の開示事項のなかから自社にとって重要性が高い事項をピックアップして開示することが有用であると考えます。例えば、多様性に関する指標のなかでも、性別・年齢などにとどまらず、自社を成長させていくうえで必要なその他の多様性要件について説明し、その実現のための指標および目標を開示することが考えられます。また、従業員の採用に関する各指標について、空きポジション/クリティカルポジションが埋まるまでの時間などの比較可能な指標を示したうえで、当該ポジションの採用がなぜ自社の戦略において重要なのか、採用の安定が自社の事業の成長、ひいては企業価値向上にどのように寄与するのかを説明することが考えられます。採用後の能力開発については、従業員一人当たりの平均研修時間や研修参加者の割合などに加え、従業員のコンピテンシー率(ある期間における評価に基づき、個々の労働者に割り当てられたコンピテンシー評価の平均値)などを開示し、自社の事業ポートフォリオに合わせた求める人材像および、人材育成の進捗度を説明することが考えられます。そのほか、財務指標と人事データを結び付けて効果検証ができるという意味で重要度の高い生産性関連指標のなかでも、人的資本投資の効率性を示す人的資本ROIを用いることで、人件費や研修費、採用費など包括的な人的資本投資に対するリターンを定量的に示すことができます。最近では、日本企業でも人的資本レポート等において人的資本ROIを開示する事例が増えており、今後は同業他社間や国際的な比較での活用も進むと考えられます。
本メルマガで概説したISO30414だけでなく、他の国際基準やガイドライン等も参考としながら、企業は自社の経営戦略と人材戦略が一体となった価値創造ストーリーを構築し、それを土台とした将来像と現状のギャップを埋めるための人的資本経営の開示を通じて、単なる情報提供を超えて投資家や社会からの信頼を高めることが求められると考えます。
図表5
人的資本可視化指針における開示事項の類型と開示のポイント

参考文献
- 1 金融庁 「第1回 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(令和7年度) 事務局説明資料」(2025年8月26日)
- 2 International Organization for Standardization, “ISO 30414: 2018: Human resource management- Guidelines for internal and external human capital reporting” (2018年12月)
- 3 International Organization for Standardization, “ISO 30414: 2025: Human resource management- Requirements and recommendations for human capital reporting and disclosure” (2025年8月)
- 4 International Organization for Standardization, “ISO 30414: 2025: Human resource management- Requirements and recommendations for human capital reporting and disclosure” (2025年8月)
- 5 International Organization for Standardization, Foreword - Supplementary information, https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
- 6 International Organization for Standardization, Foreword - Supplementary information, https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
- 7 非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」(2022年8月30日)https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf.
Opinion Leaderオピニオン・リーダー
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
コンサルタント
石丸 萌 Moe Ishimaru
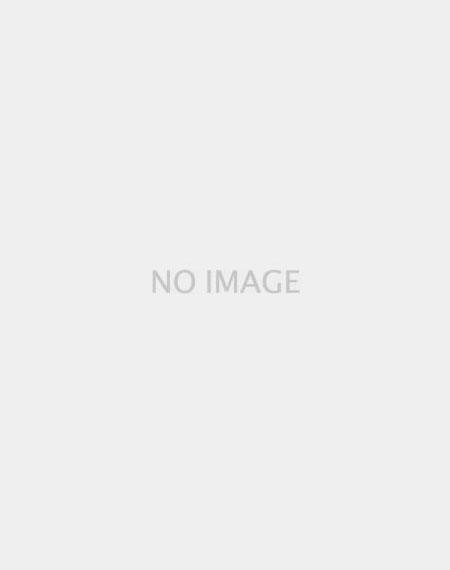
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
コンサルタント
前田 祐梨子 Yuriko Maeda
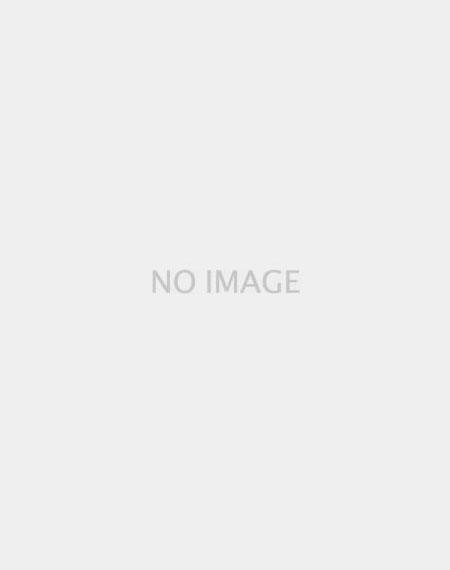
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
マネージャー
大石 英翔 Hideto Oishi